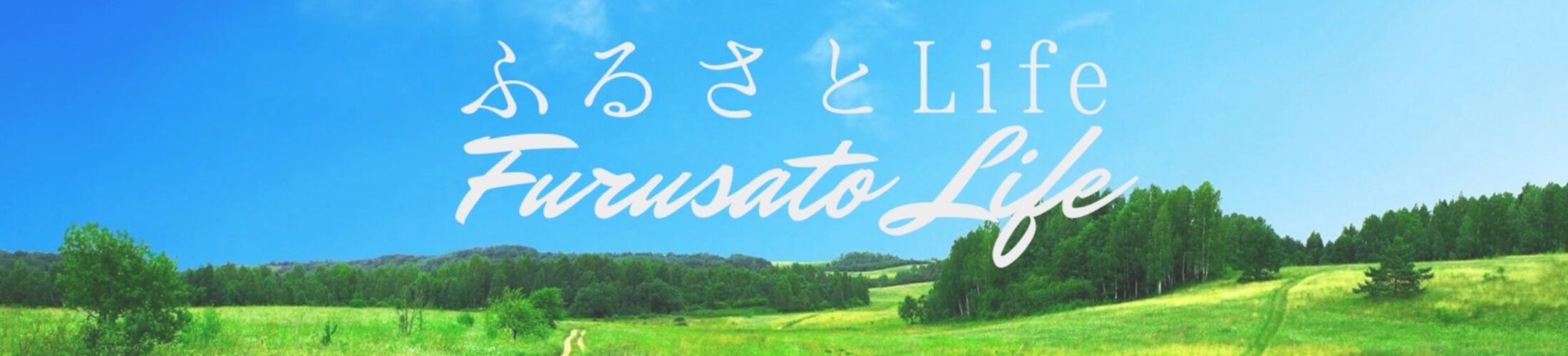建設業の経理に特化した簿記資格である「建設業経理士」をご存じですか?
建設業で経理をする方なら取得していて損はないと言われる「建設業経理士」
その理由としては、建設業の経理知識を得るという事はモチロン、
経営事項審査という建設業の入札に関する審査で加点をしてもらえます!!
経営事項審査とは「この会社の経営は良いか」という判断をする上で重要な審査であり、公共案件の入札をする際には必要な審査となります。
そうした点からも「建設業経理士」の資格はメリットがとても多い資格です。
今回は私が実際に取った「建設業経理士」についてお伝えします。
建設業経理士の資格の難易度や勉強方法、また取得している事によるメリットについても具体的に解説します。
Table of Contents
建設業経理士とは
建設業経理士は一般財団法人建設業振興基金の「建設業経理検定」に合格した者をいいます。
事務の資格で有名な資格として「日商簿記検定」がありますが、「建設業経理士」は建設業に特化した会計知識を問われる試験です。
建設業界の会計は独特の帳簿の付け方や財務諸表となっており、それらの実務知識や財務諸表を読み解く力が必要となります。
建設業経理検定は
◆1級 (建設業経理士)
◆2級 (建設業経理士)
◆3級 (建設業経理事務士)
◆4級 (建設業経理事務士)
の階層に分かれています。
そして、1級試験は3科目で構成されており、全3科目に合格して「1級資格」となります。

経営事項審査では2級から加点対象となるので目指すのは2級以上をオススメしますが、これまでの簿記知識や経理における実務経験などを踏まえて無理の無い範囲から受験していきましょう。
建設業経理士を持っているメリット
建設業経理士を持っているメリットとしては、
◆建設業の企業への就職や転職に有利になる
◆建設業で資格保有者がいると入札等でメリットがあるため、会社から重宝される
といった点があります。
具体的に説明すると、建設業界では「入札」という物がありますが、 国、地方公共団体などが発注する公共工事を直接請け負おうとする場合には、「経営事項審査」というものを必ず受けなければならない決まりがあります。
経営事項審査というのは、会社の通知表のような物なのですが、その評価項目に「建設業経理士」の資格者があり、資格保有者がいると加点となります。
さらに建設業経理士「1級」取得者は、公認会計士が監査したのと同じ価値で評価されます。
建設業の会社に建設業経理士がいると、それだけ「会社の会計処理がしっかり行われている」という信用があるという事です。
なので、建設業の事務への就職を目指す人や、建設業の経理で働いている人は是非狙いたい資格です
日商簿記の知識は必要?
建設業経理士は通常の簿記の知識に加えて建設業独自の会計知識が必要となるため、まずは日商簿記から学ぶと理解しやすいです。
毎年「日商簿記」「建設業経理士」の難易度は変動していますが、私のオススメは
日商簿記3級 → 日商簿記2級 → 建設業経理士2級 → 建設業経理士1級
という順番で、「先に日商簿記を取得してしまう」方が理解しやすくて良いのではと思います
(日商簿記はどの業界にも関係するので、汎用性があります)
全く簿記の知識が無い状態で建設業経理士を勉強すると、「?」となってしまう事が多く、会計そのものを理解に時間がかかってしまうかと思います。
日商2級は飛ばしても良いかもしれませんが、日商3級は先に取得しておきましょう。
日商簿記の方がメジャーな資格であるため、開設動画やテキストなどが充実しており勉強面においては非常にやりやすいと思います。
日商簿記自体は取得していて損はない資格ですので、是非挑戦してみて下さい。
建設業経理士はどのぐらい勉強が必要?
簿記の知識がある状態で「建設業経理士」にどのぐらい勉強が必要かというと
◇建設業経理士 2級 → 5~7カ月
◇建設業経理士 1級 → 7~1年6カ月(3科目合格)
という期間がおおよその目安になるかと思います。
ただ、1級は 「財務諸表」「財務分析」「原価計算」 の3科目があり、5年以内に全て合格して「1級合格」となります。
なので、私のオススメは
1級は1科目ずつ勉強して半年ごとに試験を受ける
という方法をオススメします
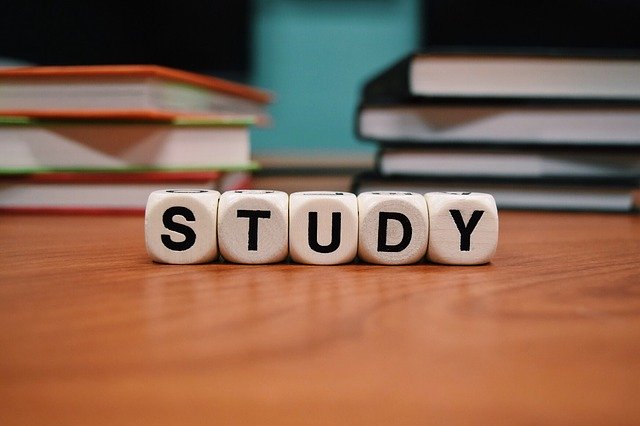
1級と2級の試験は3月と9月に実施されていますので、まず2級を6カ月の期間で合格し、その勢いのまま1級の1科目を6カ月集中して勉強していくと、合格が見えてきやすくなります。
1級の3科目をまとめて受験する方が受験料は安いですが、同日に3科目の試験を行う集中力も大変で、落ちてしまえば再受験で費用が掛かります。
慌てず半年ごとに集中して受験することを私はオススメしております。
建設業経理士の受験料
建設業経理士の受験料は下記のようになります
| 1級(1科目) | 7,410円 |
|---|---|
| 1級(2科目同時) | 10,600円 |
| 1級(3科目同時) | 13,680円 |
| 2級 | 6,280円 |
上記は消費税込みの値段になります。(2020年6月現在)
受験申込書で申し込む場合は、申込書代金310円(消費税込)を上記受験料に加算した金額となります。
インターネットで申し込む場合は、ネット申込手数料310円(消費税込)を上記受験料に加算した金額となります。

確かに1級は複数科目を同時に申し込みすると安くなりますが、よほど自身が無い限り3科目同時受験はオススメしません。
1級は内容も多くて、結構難しいです!
無理して同時受験して不合格になってしまい再受験するぐらいなら、1科目ずつ受けた方がいいと私は思います。
受験から発表まで2カ月ほどかかりますが、1級の一つの科目の受験が終わったらすぐ次の科目の勉強をしていきましょう。
もし2か月後の発表で前回受けた科目が不合格になっていた際には、次の試験で2科目受ける方法が良いと思います。
まずは1科目ずつ合格する事に集中するのがオススメです。
オススメのテキスト・勉強法
私が使っていたテキストでオススメはこちらです
ネコのイラストが可愛いですが、とても分かりやすく要点をまとめられているテキストです。
そして、過去問はこちらを使用しました
イラストは昭和が漂いますが、内容は確かです!!(笑)
そして、勉強方法は
過去問から先にやるのがオススメです!!
「過去問」をやって間違えたところを「テキスト」で確認していくと効率良く学ぶ事ができます。
そして、何回か過去問をやっていくと問題の傾向やパターンがつかめてきます。
この勉強方法で十分合格が見えてきますので、試験勉強の際には是非お試し下さい。
資格取得後も手厚い研修がある
建設業経理士に合格後は、「登録建設業経理士制度」があります。
合格後に登録講習会を修了すること等により、「登録1級建設業経理士」または「登録2級建設業経理士」の称号が付された登録証をもらえます
(期限5年間)
この登録証は今のところ使う場面は私は無いのですが、財団が主催するセミナーに割引価格で参加する事ができ、知識の習得を行う事ができます。

登録に係る手数料は、15,430円(消費税込) になりますが、勤務先等で負担をしてもらえるのであれば登録する価値は十分にあります。

取得後も知識をアップデートすることができる資格ですので、興味があれば登録をオススメします。
建設業経理士のメリットまとめ
今回は「建設業経理士」の資格について解説しました。
建設業経理士を取得する上でのメリットとしては
・建設業の経理知識の習得
・建設業事務職への就職に有利
・経営事項審査での加点
といった点があります。
自分だけでなく、会社にもメリットがある建設業経理士を是非目指してみてはいかがでしょうか。
-

-
【コツコツ貯める】子育て世代にオススメな資産形成
続きを見る
-

-
合格のコツ!「資格取得」のための7つの超効率勉強法
続きを見る